
|
さて、このような加齢にともなう基礎代謝量の減少には体組成の変化、具体的には活性組織量の減少が大きく寄与していることがわかっている。活性組織の主体をなすのは筋肉であるから、身体を構成する成分のうち、加齢にともなう筋肉の占める割合の減少(並びにおそらくは筋肉細胞の代謝活性の低下)がエネルギー必要量の低下をもたらしていると考えられる(図2)。中高年の栄養と健康とのかかわりから見て、この事実はいくつかの極めて重要な意味を持っている。詳細は後述するが、要約するとまずエネルギー需要の低下は摂食量の減少につながり、それにともなって食物中の必須栄養素など、健康の維持にとって必要な食物成分の摂取量が減少する(図3)。第2には基礎代謝の低下は、睡眠時や安静時を含む24時間を通じてのエネルギー消費量の減少をもたらすため、とくに肥満しやすい体質の人にとって加齢にともなって肥満の危険性が増すことになる。事実、中年から高齢にかけて体組成の中に脂肪の占める割合が増加する傾向がみられている。最近のヒト集団を対象とした系統的調査や動物実験の結果によれば、肥満者は非肥満者に比べ平均寿命が顕著に短いといわれている。基礎代謝の高低が寿命に影響するかどうかについては明確な結論は得られていないものの、ラットを用いた観察結果では、若年期からのエネルギー摂取量の制限が肥満を防ぎ、最長寿命、平均寿命ともに低エネルギー摂取の度合いとの間に負の関係があることが明らかにされている(図4)。
図2 基礎代謝に及ぼす各臓器の影響(Korechevsky)
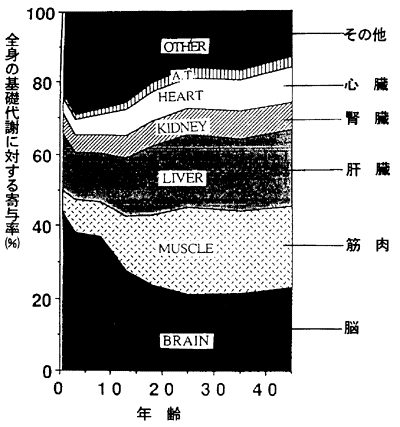
前ページ 目次へ 次ページ
|

|